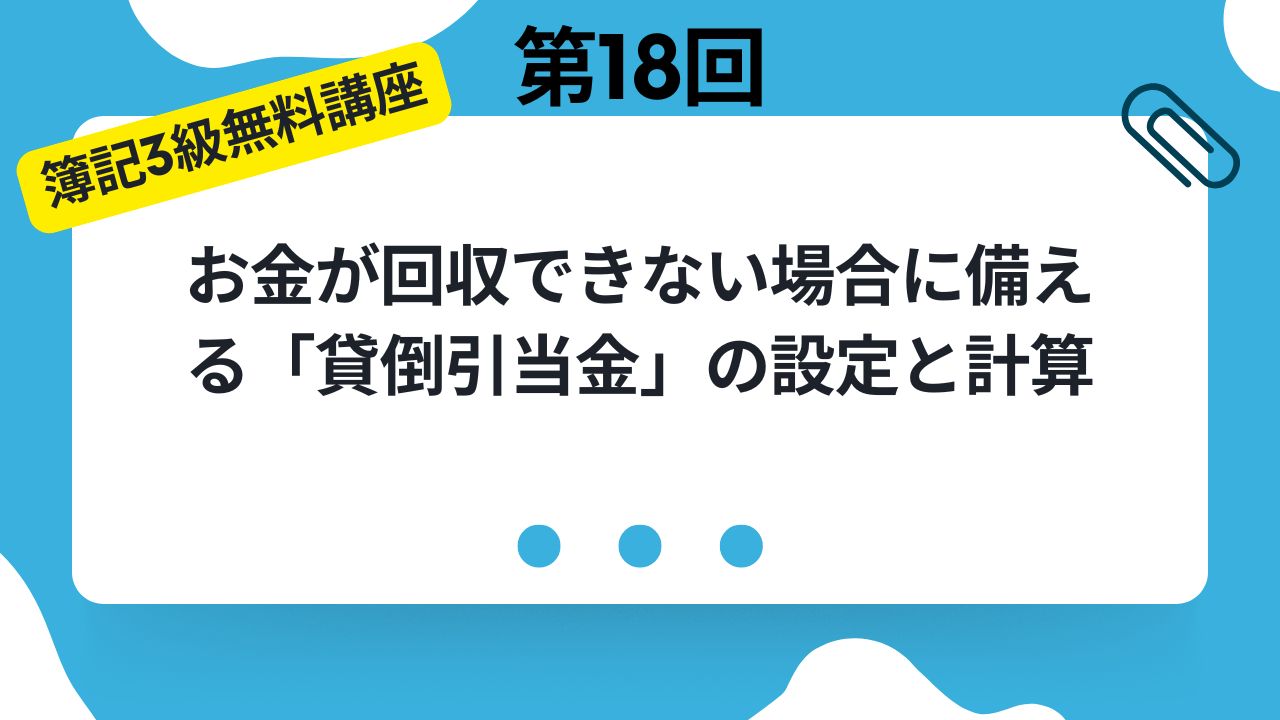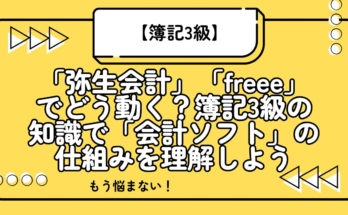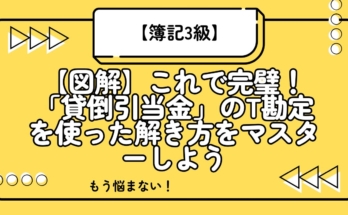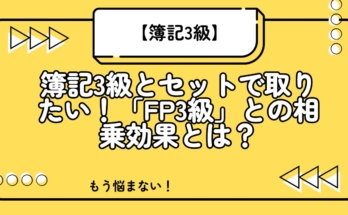こんにちは!「簿記3級合格へ導く!無料Web講座」へようこそ。講師の簿記3級講座です。
第17回では、決算整理の第一弾として、「しーくり、くりしー」の仕訳で正しい「売上原価」を計算する方法を学びました。これで、売上とそれに対応する原価がハッキリしましたね。
さて、決算整理は「会社の正しい成績」を出すための作業です。
ここで、「売掛金」や「受取手形」(あわせて「売上債権」といいます)に目を向けてみましょう。試算表には「売掛金 1,000,000円」と載っているかもしれません。
しかし、その100万円、本当に全額、来年回収できるでしょうか?
取引先が倒産して、お金が回収できなくなるかもしれません。この「売掛金などが回収できなくなること」を「貸倒れ」といいます。
今回は、この「貸倒れ」というリスクに、決算であらかじめ備えておくための重要な処理、「貸倒引当金」の設定と計算方法をマスターしましょう!
今日のゴール
- 「貸倒れ」とは何か、なぜ事前に備える必要があるのかがわかる
- 「貸倒引当金」(資産のマイナス)と「貸倒引当金繰入」(費用)という2つの勘定科目の役割がわかる
- (期末の債権残高 × 実績率)で「必要な見積額」を計算できる
- 「差額補充法」の意味を理解し、決算整理仕訳ができる
「貸倒引当金」とは? – リスクに備える引当金
もし、来期に10万円の売掛金が貸倒れたら、その期に10万円の「貸倒損失(費用)」が発生し、利益がガクッと減ってしまいます。
しかし、その貸倒れの原因となった「売上(収益)」は、今期(今年)に計上されています。
これでは、収益(今期)と費用(来期)の対応が取れておらず、正しい期間の利益が計算できません(=発生主義の違反)。
そこで、簿記では「保守主義の原則」(将来の損失には早めに備えよう)という考え方に基づき、決算の時点で「今ある売掛金のうち、来期にこれくらいは貸倒れるかもしれないな…」という金額を見積もり、あらかじめ今期の費用として計上します。
この「貸倒れの見積額」を計上するための勘定科目が「貸倒引当金」です。
2つの新・勘定科目
この処理では、2つの新しい勘定科目を使います。役割をしっかり区別してください。
- 貸倒引当金繰入
- グループ: 費用
- 役割: 貸倒れの見積額を、今期の費用として計上するための勘定科目。損益計算書(P/L)に行きます。
- 貸倒引当金
- グループ: 資産のマイナス(評価勘定)
- 役割: 「売掛金」や「受取手形」の価値を間接的に減らすための勘定科目。「売掛金から、これくらいは回収できないかも」という控除(マイナス)項目として、貸借対照表(B/S)に行きます。
「貸倒引当金繰入」(費用)を使って、「貸倒引当金」(資産のマイナス)という“貸倒れに備える引当金”を設定する、というイメージです。
貸倒引当金の計算方法 – 「差額補充法」
では、いくら費用(繰入額)を計上すればよいのでしょうか。
簿記3級では「差額補充法」という方法を使います。これは「足りない分だけ補充する」方法です。
ステップ1:今期末に必要な「引当金のゴール額」を計算する
まず、期末時点で「売掛金」「受取手形」がいくらあるかを確認し、それに「貸倒実績率(過去の経験から見積もった貸倒れ率)」を掛けて、最終的に必要な引当金のゴール額(要設定額)を計算します。
ステップ2:現在の「引当金の残高」を確認する
決算整理前残高試算表に、「貸倒引当金」の残高が残っている場合があります。
これは、前期末に設定した引当金が、今期使われずに残ったものです。
ステップ3:「足りない金額」だけを「繰り入れる」(仕訳する)
ステップ1で計算した「ゴール額」になるように、ステップ2の「現在の残高」との差額だけを補充(繰り入れ)します。
設例でマスター!「差額補充法」の仕訳
この流れを、具体的な設例で見ていきましょう。
【設例】
- 決算日になった。
- 期末の売掛金残高は800,000円、受取手形残高は200,000円であった。
- 貸倒実績率は 2% とする。
- (問)決算整理前の貸倒引当金残高が 5,000円 あった場合の仕訳は?
【考え方(差額補充法)】
ステップ1:ゴール額(要設定額)の計算
(800,000円 + 200,000円) × 2% = 1,000,000円 × 2% = 20,000円
→ 決算後の貸倒引当金の残高を 20,000円 にすることがゴールです。
ステップ2:現在の残高の確認
決算整理前の残高は 5,000円 です。
ステップ3:繰入額(仕訳額)の計算
20,000円(ゴール) - 5,000円(現在) = 15,000円(補充する額)
【決算整理仕訳】
この15,000円(費用)を「繰り入れ」て、同額の「引当金」(資産のマイナス)を増やします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | 15,000 | 貸倒引当金 | 15,000 |
T勘定での動き
この仕訳によって、T勘定(総勘定元帳)がどう動くか確認しましょう。
| 貸倒引当金(資産のマイナス) | |
|---|---|
| 借方(減少) | 貸方(増加) |
| (整理前) 5,000 (②) (整理仕訳) 15,000 (③) |
|
| 決算後残高: 20,000円(貸方) → ゴール(①)達成! |
|
| 貸倒引当金繰入(費用) | |
|---|---|
| 借方(発生) | 貸方(取消) |
| (整理仕訳) 15,000 (③) | |
| 今期の費用: 15,000円 → 損益計算書(P/L)へ |
|
※もし、決算整理前の貸倒引当金残高が「0円」だったら?
(ゴール 20,000円)-(現在 0円)= 20,000円 が繰入額となります。
貸借対照表(B/S)での表示方法
この決算整理の結果、貸借対照表(B/S)の「資産の部」は以下のようになります。
貸借対照表(一部)
【資産の部】
- 売掛金
- 800,000
- 受取手形
- 200,000
- 貸倒引当金
- △ 20,000
- (差引) 980,000
このように、「貸倒引当金」は、売掛金や受取手形からマイナスする形で表示されます。
「債権は100万円あるけど、実質的な価値は98万円くらいだよね」ということを報告するわけです。
POINTまとめ
- 貸倒れとは、売掛金などが回収できなくなること。
- 貸倒引当金は、将来の貸倒れに備えるための見積額(資産のマイナス)。
- 貸倒引当金繰入は、引当金を設定するための今期の費用。
- 計算方法は「差額補充法」(足りない分だけ補充する)。
- 当期の繰入額 =(期末債権残高 × 実績率)-(決算整理前の引当金残高)
- 決算整理仕訳は、(借)貸倒引当金繰入 / (貸)貸倒引当金 となる。
ミニクイズ
お疲れ様でした!「しーくり、くりしー」に続く、決算整理の重要論点でした。計算方法をしっかり押さえましょう。
【Q1】決算整理で、貸倒れの見積額を当期の費用として計上する際に使う「費用」の勘定科目はどれ?
- 貸倒損失
- 貸倒引当金
- 貸倒引当金繰入
答えを見る
【A1】3. 貸倒引当金繰入
解説:「貸倒引当金」は資産のマイナス項目。「貸倒損失」は、引当金を超えて実際に貸倒れが発生したときに使う費用です。決算整理で「設定」する費用は「繰入」です。
【Q2】期末の売掛金残高が 300,000円、貸倒実績率が 3% だった。決算整理前の貸倒引当金残高は 4,000円である。決算整理仕訳で「貸倒引当金繰入」として計上する金額はいくら?
- 4,000円
- 5,000円
- 9,000円
答えを見る
【A2】2. 5,000円
解説:
①ゴール(要設定額)= 300,000円 × 3% = 9,000円
②現在の残高 = 4,000円
③繰入額 = 9,000円 - 4,000円 = 5,000円
これで、「商品」と「債権」という2つの大きな資産の調整が終わりました。
次回は、もう一つの大きな資産、「建物」や「備品」の調整です。
第8回で基本を学んだ、あの「減価償却」を決算整理仕訳として、より実践的に(期中購入のケースなど)学んでいきます!お楽しみに!