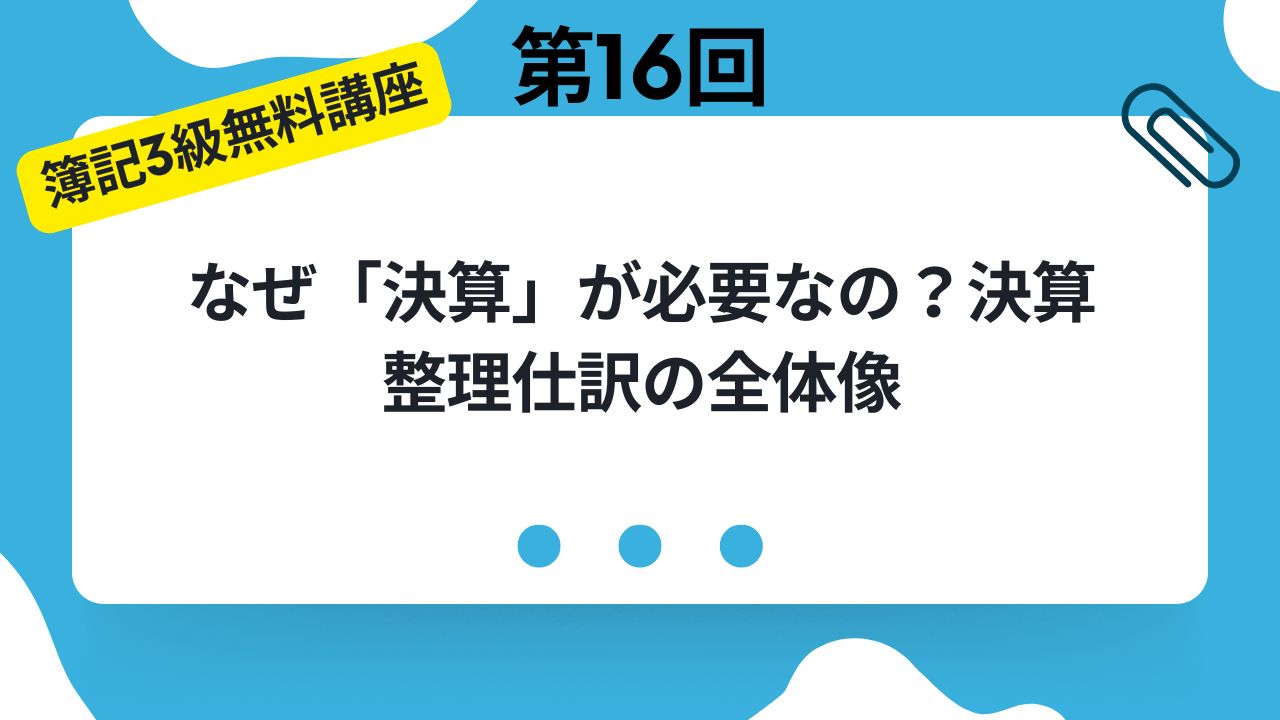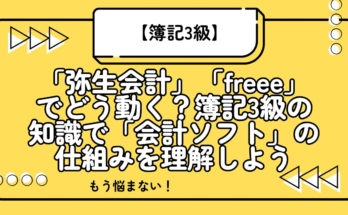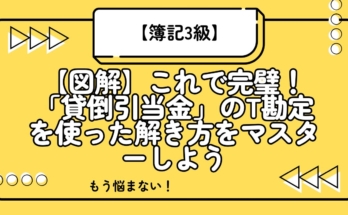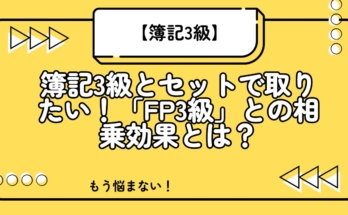こんにちは!「簿記3級合格へ導く!無料Web講座」へようこそ。
第3部(第13回〜第15回)では、日々の「仕訳」を「転記」し、「試算表」を作成することで、転記ミスがないかを確認する流れを学びました。試算表の借方合計と貸方合計が一致したときは、達成感がありましたね!
さて、これで全ての勘定科目の「残高」が一覧になりました。
「じゃあ、この残高試算表の数字をそのまま使って、会社の成績表(財務諸表)が作れる!」
…と、思いきや、実はまだこの試算表は「未完成」なのです。
なぜなら、あの日々作成した試算表は、あくまで「その日までの取引」を集計しただけ。
会社の正しい1年間の成績を出すためには、年に一度、期末にだけ行う特別な「調整」作業が必要になります。
この作業こそが、簿記のクライマックス「決算」です。
今回から始まる第4部「決算整理編」では、この決算作業の心臓部である「決算整理仕訳」について、8回にわたって徹底的に学んでいきます!
今日のゴール
- 「決算」とは何か、その目的を理解する
- なぜ試算表の数字をそのまま使えず、「決算整理」が必要なのか、その理由がわかる
- 簿記の重要な考え方「発生主義」のキホンを理解する
- これから第4部で学ぶ「決算整理仕訳」の全体のマップ(全体像)を掴む
「決算」とは? – 年に一度の健康診断
決算とは、会社の会計期間(通常は1年間)の終わり(期末)に、その1年間の「儲け(経営成績)」と、期末時点での「財産(財政状態)」を確定させるための一連の手続きをいいます。
会社にとって、年に一度の「健康診断」のようなものです。
この健康診断の結果をまとめたものが、最終ゴールである「損益計算書(P/L)」と「貸借対照表(B/S)」というわけです。
なぜ「決算整理」が必要なの?
私たちが第3部で作った試算表は、正しくは「決算整理前残高試算表」と呼ばれます。つまり、「決算整理をする前の(未完成な)試算表」です。
なぜ、この試算表は未完成なのでしょうか?主な理由は3つあります。
理由①:期末にしか計算しない項目があるから
例えば、第8回で学んだ「減価償却」を思い出してください。
会社が車(車両運搬具)を使っていても、その価値の減少(減価償却費)を「毎日」仕訳してはいませんでしたよね?
こうした「時間の経過」とともに発生する費用は、期末にまとめて1年分を計算するルールになっています。
この計算を決算整理前試算表は反映していないのです。
理由②:現金の動きと「儲け」のタイミングがズレるから
これが最も重要な理由です。
例えば、会社の決算日が3月31日だとします。
3月分の給料の支払日が「翌月4月10日」だった場合、どうでしょう?
決算整理前試算表には、3月31日時点でまだ払っていないため、「3月分の給料」は費用として一切記録されていません。
しかし、従業員は3月中に働いているので、その分の給料は「3月の費用」として計上すべきです。
このように、お金の支払い(キャッシュ・ベース)と、費用の発生(アクルーアル・ベース)の「ズレ」を修正する必要があります。
この「お金の動きに関係なく、経済的な事実が発生した時点で収益や費用を認識する」という考え方を、簿記の超重要原則である「発生主義」といいます。
理由③:売れた商品の「原価」が計算されていないから
私たちは、商品を仕入れたら(借)仕入、売り上げたら(貸)売上、と仕訳してきました。
しかし、「仕入」勘定は「1年間に買った商品の総額」を示しているだけで、「売れた分の商品の原価(売上原価)」がいくらなのか、まったく分かりません。
決算では、期末に倉庫の在庫(売れ残り)を数え(=棚卸)、売上原価を正しく計算する作業が必要です。
「決算整理仕訳」とは?
上記のような「試算表のズレ」を修正するために行う、決算時にのみ行う特別な仕訳のことを、「決算整理仕訳」といいます。
この決算整理仕訳を行うことで、決算整理前試算表の数字が「発生主義」に基づいた正しい数字にアップデートされ、会社の本当の成績を計算できる状態になるのです。
イラスト解説:決算整理の流れ
簿記は「仕訳→転記→試算表」で終わりではありません。この先に決算整理が待っています。全体の流れを掴みましょう。
簿記の一連の流れ(決算まで)
① 日々の取引
(仕訳 → 転記)
⬇
② 決算整理前残高試算表 の作成
(=未完成な試算表)
⬇
③ 決算整理仕訳 の実施
(ズレを修正する特別な仕訳)
⬇
④ 決算整理後残高試算表 の作成
(=完成版の試算表)
⬇
⑤ 財務諸表(B/S・P/L) の作成
(=最終ゴール!)
今回から学ぶ「第4部」は、この流れの中の③「決算整理仕訳」をマスターするセクションです!
第4部で学ぶ「決算整理仕訳」の全体像
決算整理仕訳には、いくつかの決まったパターンがあります。第4部では、以下の7つの重要テーマ(8回分)を順番に攻略していきます。これらが簿記3級の「ラスボス」たちです!
- 売上原価の計算(第17回):売れ残り在庫を数えて、本当の売上原価を計算する。
- 貸倒引当金の設定(第18回):売掛金が回収できない場合に備える。
- 減価償却(第19回):固定資産の価値の減少を費用として計上する。(第8回の続き)
- 費用の繰延べ(第20回):今年払ったけど、来年の分の費用(前払費用)。
- 費用の見越し(第21回):今年はまだ払ってないけど、今年の分の費用(未払費用)。
- 収益の繰延べ(第22回):今年受け取ったけど、来年の分の収益(前受収益)。
- 収益の見越し(第23回):今年はまだ貰ってないけど、今年の分の収益(未収収益)。
(※第20回〜第23回は「経過勘定」と呼ばれ、特に重要です!)
POINTまとめ
- 決算とは、1年間の正しい経営成績と財政状態を計算するための、年に一度の手続き。
- 日々の取引を集計しただけの「決算整理前残高試算表」は、まだ未完成である。
- 「発生主義」とは、お金の動きに関係なく、事実が発生した時点で収益・費用を認識する考え方。
- 決算整理仕訳とは、試算表のズレを「発生主義」に基づいて修正するための、期末に行う特別な仕訳。
- 決算整理仕訳には、売上原価の計算、減価償却、費用の見越し・繰延べなど、決まったパターンがある。
ミニクイズ
お疲れ様でした!いよいよラスボス戦(決算)に突入する心構えはできましたか?クイズで確認してみましょう。
【Q1】決算整理前残高試算表の数字を、そのまま決算書(B/S, P/L)の作成に使えない主な理由として、誤っているものはどれ?
- 日々の転記ミスが残っている可能性があるから。
- 減価償却費など、期末にまとめて計算する項目が反映されていないから。
- お金の支払いと費用の発生タイミングのズレ(発生主義)が修正されていないから。
答えを見る
【A1】1. 日々の転記ミスが残っている可能性があるから。
解説:試算表は「転記ミスを発見するため」に作成します(第14回)。試算表の借方・貸方が一致した時点で、転記ミスは(ほぼ)無い、という前提で決算整理に進みます。2と3が、決算整理が必要な正しい理由です。
【Q2】お金の受取りや支払いに関係なく、経済的な事実(働いた、モノを使った)が発生した時点で収益や費用を認識する考え方を何というか?
- 現金主義
- 発生主義
- 試算主義
答えを見る
【A2】2. 発生主義
解説:簿記の基本となる考え方です。「現金主義」は、お金が動いた時だけ記録する古い考え方です。決算整理は、この「発生主義」を徹底するために行われます。
今回は、決算整理の「なぜ?」と「何をやるか?」という全体像を掴みました。ここが分かれば、あとは一つ一つの仕訳をパズルのように覚えていくだけです。
次回は、さっそく決算整理の第一弾!「仕入」勘定の数字を「本当の売上原価」に修正する、あの有名なおまじない「しーくり、くりしー」の意味を徹底解説します!お楽しみに!