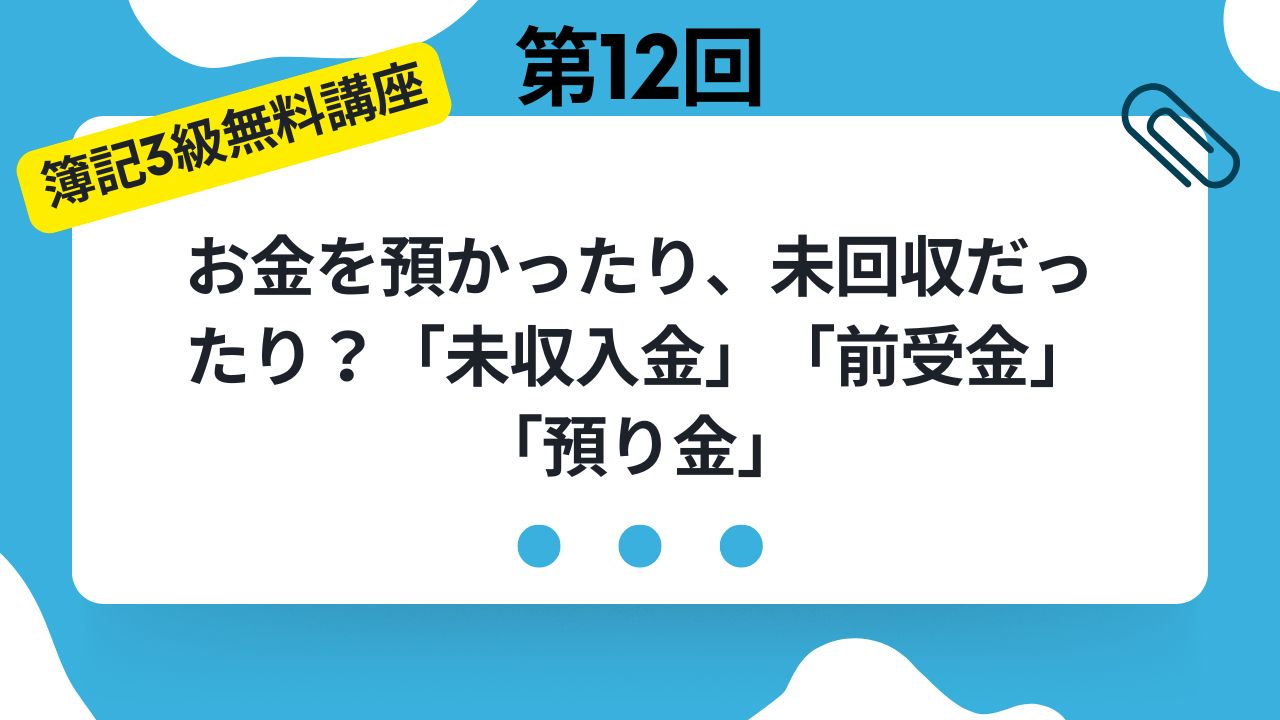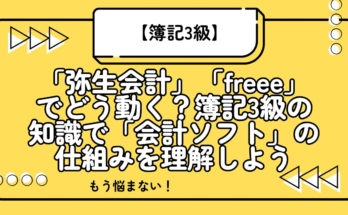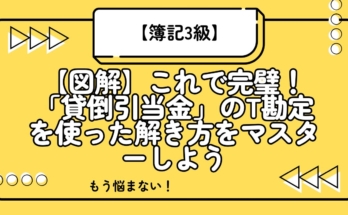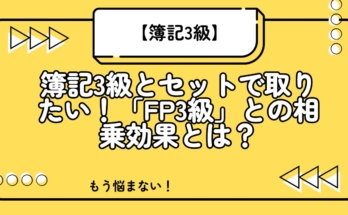こんにちは!「簿記3級合格へ導く!無料Web講座」へようこそ。
第11回では、「立替金」「貸付金」「前払金」という、一時的に発生する「権利」(資産)について学びました。お金を立て替えたり、手付金を払ったりする取引でしたね。
今回は、それらと対になるような、ちょっと特殊な取引の第2弾です。
具体的には、
- 本業以外(商品の販売以外)で、まだお金をもらっていない(未回収)
- 商品の代金を、商品を引き渡す「前」にもらった(前受け)
- 従業員や税務署に「後で渡す」ためにお金を一時的に「預かる」
といったケースです。
今回は、これらを表す勘定科目「未収入金」「前受金」「預り金」の3つを徹底的にマスターしましょう!
今日のゴール
- 「売掛金」と「未収入金」(資産)の違いを明確に理解し、仕訳ができる
- 商品の手付金を受け取った時の「前受金」(負債)の仕訳ができる
- 商品を納品した時に「前受金」を「売上」に振り替える仕訳ができる
- 給料から天引きする「預り金」(負債)の仕訳ができる
「未収入金」とは?(商品以外の未回収代金)
「未収入金」とは、本業の商品売買「以外」の取引で発生した、まだ受け取っていない代金のことです。
例えば、会社で使っていた古い備品(固定資産)を売却したり、第10回で学んだ「受取手数料」が後払いになったりした場合に使います。
これは「後でお金を受け取る権利」なので、「資産」のグループです。
【最重要】「売掛金」と「未収入金」の使い分け
どちらも「後でお金をもらう権利」(資産)ですが、簿記では厳密に区別します。このルールは試験で100%問われます!
「後で受け取る権利」の使い分け
① 本業の「商品」を売った
⬇
「売掛金」
(資産)
② それ以外ぜんぶ
(古い備品、建物の売却)
(手数料、家賃の未収)
⬇
「未収入金」
(資産)
設例①:固定資産を売却し、代金が未回収
【設例1】会社で使っていた古いパソコン(備品)を5,000円で売却し、代金は来月受け取ることになった。
【考え方】
- パソコン(備品)は「商品」ではない。したがって「未収入金」を使います。
- 「未収入金」(資産)が5,000円増えた → 借方(左)に「未収入金 5,000」
- 「備品」(資産)が5,000円減った → 貸方(右)に「備品 5,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 5,000 | 備品 | 5,000 |
※借方は「売掛金」ではありません!
※(参考)実際は備品の元の値段や減価償却を考慮しますが、ここではまず「未収入金」の使い方を覚えてください。
「前受金」とは?(商品の手付金を受け取る)
「前受金(まえうけきん)」とは、商品を販売する契約をした際に、代金の一部を手付金や内金として「先」に受け取ったときに使う勘定科目です。
第11回の「前払金」(資産)のちょうど反対です。
これは「後でその分の商品を引き渡さなければならない義務」なので、「負債」のグループです。
この時点ではまだ「売上」(収益)ではない、というのが最重要ポイントです。「売上」は、商品を実際に引き渡した(納品した)ときに初めて発生します。
設例②:手付金(前受金)を受け取った
【設例2】D商店から商品80,000円の注文を受け、手付金として20,000円を現金で受け取った。
【考え方】
- 「現金」(資産)が20,000円増えた → 借方(左)に「現金 20,000」
- 「前受金」(負債)が20,000円増えた(後で商品を引き渡す義務) → 貸方(右)に「前受金 20,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 20,000 | 前受金 | 20,000 |
※貸方は「売上」ではありません!
設例③:商品を納品し、残金を受け取った
【設例3】D商店に注文の商品80,000円を引き渡した。代金のうち、手付金20,000円を差し引き、残額60,000円は掛けとした。
【考え方】
ここで初めて「売上」が登場します。
- 商品を引き渡したので、「売上」(収益)が全額の80,000円発生した → 貸方(右)に「売上 80,000」
- 先に受け取った手付金(前受金)の「義務」がなくなったので、「前受金」(負債)が20,000円減った → 借方(左)に「前受金 20,000」
- 残りの代金は後受け(掛け)なので、「売掛金」(資産)が60,000円増えた → 借方(左)に「売掛金 60,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 20,000 | 売上 | 80,000 |
| 売掛金 | 60,000 |
※第11回の「前払金」とセットで、試験の超頻出論点です!
「預り金」とは?(他人の分を一時的に預かる)
「預り金」とは、後で本人(従業員など)の代わりに第三者(税務署、社会保険事務所など)へ支払うために、一時的にお金を預かったときに使う勘定科目です。
これも「後で支払わなければならない義務」なので、「負債」のグループです。
簿記3級で最もよく出るのは、従業員の給料から天引きする「源泉所得税」や「社会保険料」の処理です。
設例④:給料を支払い、税金などを天引きした(負債の発生)
【設例4】従業員の給料総額250,000円から、源泉所得税10,000円と社会保険料30,000円を差し引き(天引きし)、残額210,000円を普通預金口座から振り込んだ。
【考え方】
会社が支払う「費用」は、天引き前の「総額」です。
- 「給料」(費用)が総額の250,000円発生した → 借方(左)に「給料 250,000」
- 天引きした所得税と社会保険料(合計40,000円)は、後で税務署などに支払う「義務」なので、「預り金」(負債)が40,000円増えた → 貸方(右)に「預り金 40,000」
- 実際に従業員に払ったお金、「普通預金」(資産)が210,000円減った → 貸方(右)に「普通預金 210,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料 | 250,000 | 預り金 | 40,000 |
| 普通預金 | 210,000 |
設例⑤:預り金を納付した(負債の減少)
【設例5】上記設例4で預かった源泉所得税と社会保険料の合計40,000円を、現金で税務署などに納付した。
【考え方】
- 「預り金」(負債)が40,000円減った(義務を果たした) → 借方(左)に「預り金 40,000」
- 「現金」(資産)が40,000円減った → 貸方(右)に「現金 40,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 40,000 | 現金 | 40,000 |
POINTまとめ
- 未収入金(資産):本業の「商品」以外のものが未回収のときの権利。(↔ 売掛金)
- 前受金(負債):「商品」を渡す前に手付金を受け取ったときの義務。(↔ 前払金)
- → 商品を渡したときに「売上」に振り替える。
- 預り金(負債):給料から天引きした税金など、第三者に支払うために一時的に預かったお金。
- 「売掛金 vs 未収入金」と「買掛金 vs 未払金」の使い分けは、絶対にマスターすること!
ミニクイズ
お疲れ様でした!似たような名前の勘定科目がたくさん出てきましたね。しっかり区別できるか、クイズで確認しましょう。
【Q1】商品200,000円の注文を受け、手付金として50,000円が普通預金に振り込まれた。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 普通預金 50,000 / (貸) 売上 50,000
- (借) 普通預金 50,000 / (貸) 前受金 50,000
- (借) 普通預金 50,000 / (貸) 未収入金 50,000
答えを見る
【A1】2. (借) 普通預金 50,000 / (貸) 前受金 50,000
解説:商品はまだ引き渡していません。先に受け取った手付金は「前受金」(負債)として処理します。この時点では「売上」(収益)は発生しません。
【Q2】従業員の給料300,000円から、源泉所得税15,000円を天引きし、残額を現金で支払った。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 給料 285,000 / (貸) 現金 285,000
- (借) 給料 300,000 / (貸) 現金 285,000 / (貸) 立替金 15,000
- (借) 給料 300,000 / (貸) 現金 285,000 / (貸) 預り金 15,000
答えを見る
【A2】3. (借) 給料 300,000 / (貸) 現金 285,000 / (貸) 預り金 15,000
解説:費用である「給料」は総額の300,000円で計上します。天引きした15,000円は、後で税務署に納付する「預り金」(負債)です。
【Q3】会社が所有する土地(商品ではない)を1,000,000円で売却し、代金は来月受け取ることになった。このときの借方(左側)の勘定科目として正しいものはどれ?
- 売掛金
- 未収入金
- 前払金
答えを見る
【A3】2. 未収入金
解説:土地は本業の「商品」ではありません。商品以外のものを売却して、代金が未回収の場合は「未収入金」(資産)を使います。(貸方は「土地」などになります)
これで、第2部「仕訳マスター編」は終了です!お疲れ様でした!
「現金」から始まり、「売上」「仕入」、「掛け」や「手形」、そして「固定資産」や「費用・収益」、最後に「特殊な取引」まで、簿記3級で必要な日々の仕訳はほぼすべて網羅しました。
さて、毎日たくさん切った仕訳(ジャーナリング)ですが、このままでは「今、現金はいくら残ってるの?」「A社への売掛金は合計いくら?」というのがサッパリわかりません。
次回からの第3部では、このバラバラの仕訳を集計し、確認する作業「転記」と「試算表」について学んでいきます!いよいよ、簿記の全体像が見えてきますよ。お楽しみに!