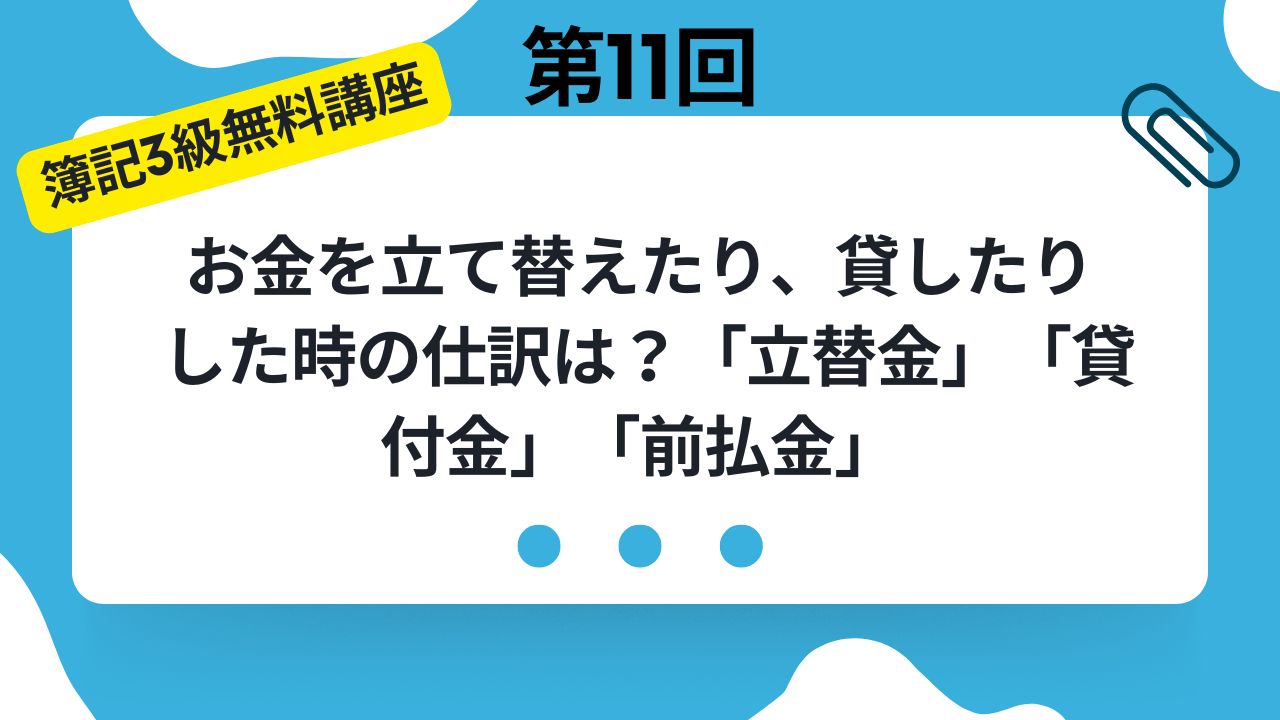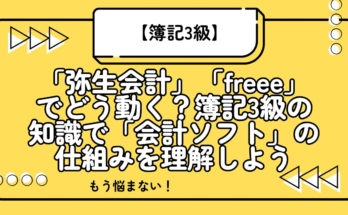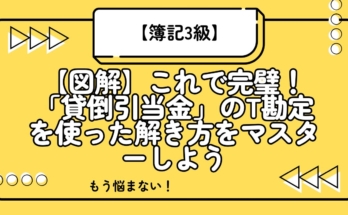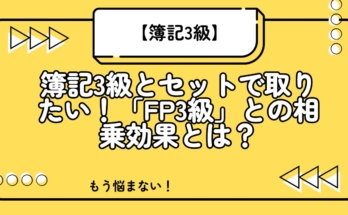こんにちは!「簿記3級合格へ導く!無料Web講座」へようこそ。
第10回では、「受取手数料」や「受取利息」など、本業の「売上」以外の様々な「収益」について学びました。収益は「貸方(右側)」に書く、がルールでしたね。
さて、今回は「費用」でも「収益」でもない、ちょっと特殊な取引を見ていきます。
例えば、従業員が使うお金を一時的に会社が立て替えたり、取引先にお金を貸したり、商品の手付金を先に支払ったり…。
これらのお金は、最終的には戻ってくる(またはモノに変わる)予定のものです。
今回は、こうした取引で使う「立替金」「貸付金」「前払金」という3つの勘定科目をマスターします。これらはすべて、「後で何かを受け取る権利」を表す「資産」のグループです。
今日のゴール
- 従業員や取引先のお金を立て替えた時の「立替金」(資産)の仕訳ができる
- 取引先にお金を貸した時の「貸付金」(資産)の仕訳ができる
- 貸したお金の利息(受取利息)を受け取った時の仕訳がわかる
- 商品の手付金(内金)を支払った時の「前払金」(資産)の仕訳ができる
- 手付金を払った商品を受け取った時の「仕入」への振替仕訳ができる
「立替金」とは?(他人の分を一時的に支払う)
「立替金」とは、従業員や取引先が本来支払うべきお金を、会社が一時的に立て替えて支払ったときに使う勘定科目です。
これは「後でそのお金を返してもらう権利」なので、「資産」のグループです。
- 資産が増えたら(立て替えたら) → 借方(左側)に「立替金」
- 資産が減ったら(返してもらったら) → 貸方(右側)に「立替金」
設例①:立替金を支払った
【設例1】従業員Aさんが個人的に購入した生命保険の保険料10,000円を、会社の現金で立て替えて支払った。
【考え方】
- 「立替金」(資産)が10,000円増えた(後でAさんから返してもらう権利) → 借方(左)に「立替金 10,000」
- 「現金」(資産)が10,000円減った → 貸方(右)に「現金 10,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 立替金 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
※会社の費用(福利厚生費など)ではない点に注意!あくまで「立て替え」です。
設例②:立替金を回収した
【設例2】上記設例1の立替金10,000円を、Aさんから現金で回収した。
【考え方】
- 「現金」(資産)が10,000円増えた → 借方(左)に「現金 10,000」
- 「立替金」(資産)が10,000円減った(権利が消滅した) → 貸方(右)に「立替金 10,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 10,000 | 立替金 | 10,000 |
※(参考)給料日に給料から天引き(相殺)する場合もあります。その場合は(借)給料 XXX / (貸)立替金 10,000, (貸)普通預金 YYY となります。
「貸付金」とは?(お金を貸す)
「貸付金」とは、取引先や従業員などに、利息を取る約束(または取らない約束)でお金を貸したときに使う勘定科目です。
これも「後で元本(貸したお金)を返してもらう権利」なので、「資産」のグループです。
- 資産が増えたら(貸したら) → 借方(左側)に「貸付金」
- 資産が減ったら(返してもらったら) → 貸方(右側)に「貸付金」
設例③:お金を貸し付けた
【設例3】取引先B社に、返済期間1年、年利5%の約束で、300,000円を当座預金から振り込んで貸し付けた。
【考え方】
- 「貸付金」(資産)が300,000円増えた(後で返してもらう権利) → 借方(左)に「貸付金 300,000」
- 「当座預金」(資産)が300,000円減った → 貸方(右)に「当座預金 300,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸付金 | 300,000 | 当座預金 | 300,000 |
設例④:貸付金を利息とともに回収した
【設例4】B社から、貸付金の元本300,000円と、利息15,000円(300,000円×5%)の合計315,000円が、当座預金口座に振り込まれた。
【考え方】
これは3つの要素が動いています。
- 「当座預金」(資産)が合計315,000円増えた → 借方(左)に「当座預金 315,000」
- 「貸付金」(資産)が300,000円減った(元本を回収した) → 貸方(右)に「貸付金 300,000」
- 「受取利息」(収益)が15,000円発生した(儲かった) → 貸方(右)に「受取利息 15,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 315,000 | 貸付金 | 300,000 |
| 受取利息 | 15,000 |
「前払金」とは?(商品の手付金・内金を支払う)
「前払金」とは、商品を仕入れる契約をした際に、代金の一部を手付金や内金として先に支払ったときに使う勘定科目です。
これは「後でその分の商品を受け取る権利」なので、「資産」のグループです。
非常に重要なポイントは、この時点ではまだ「仕入」(費用)ではない、ということです。「仕入」は、商品が実際に納品された(受け取った)ときに初めて発生します。
設例⑤:手付金(前払金)を支払った
【設例5】C商店に商品500,000円を注文し、手付金として100,000円を現金で支払った。
【考え方】
- 「前払金」(資産)が100,000円増えた(後で商品をもらう権利) → 借方(左)に「前払金 100,000」
- 「現金」(資産)が100,000円減った → 貸方(右)に「現金 100,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
※借方は「仕入」ではありません!
設例⑥:商品を受け取り、残金を支払った(最重要!)
【設例6】C商店から注文していた商品500,000円が納品された。代金のうち、手付金100,000円を差し引き、残額400,000円は掛けとした。
【考え方】
ここで初めて「仕入」が登場します。
- 商品を受け取ったので、「仕入」(費用)が全額の500,000円発生した → 借方(左)に「仕入 500,000」
- 先に払った手付金(前払金)の「権利」がなくなったので、「前払金」(資産)が100,000円減った → 貸方(右)に「前払金 100,000」
- 残りの代金は後払い(掛け)なので、「買掛金」(負債)が400,000円増えた → 貸方(右)に「買掛金 400,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 500,000 | 前払金 | 100,000 |
| 買掛金 | 400,000 |
※この「前払金を仕入に充当する」仕訳は、試験で非常に狙われやすい論点です!
POINTまとめ
- 「立替金」「貸付金」「前払金」は、すべて「資産」のグループ(発生したら借方)。
- 立替金:他人の分を一時的に支払った(後でお金を返してもらう権利)。
- 貸付金:お金を貸した(後でお金(元本)を返してもらう権利)。
- ※受け取る利息は「受取利息」(収益)。
- 前払金:商品の手付金・内金を支払った(後で商品を受け取る権利)。
- 「前払金」は、商品を受け取ったときに「仕入」勘定に振り替える。
ミニクイズ
お疲れ様でした!「権利」を表す資産グループ、理解できましたか?クイズで力試しをしてみましょう。
【Q1】取引先が負担すべき送料5,000円を、当社の現金で立て替えて支払った。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 通信費 5,000 / (貸) 現金 5,000
- (借) 立替金 5,000 / (貸) 現金 5,000
- (借) 貸付金 5,000 / (貸) 現金 5,000
答えを見る
【A1】2. (借) 立替金 5,000 / (貸) 現金 5,000
解説:「取引先が負担すべき」お金を支払ったので、「立替金」(資産)が発生します。当社の費用(通信費)ではありません。
【Q2】商品300,000円を注文し、手付金として50,000円を普通預金から振り込んだ。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 仕入 50,000 / (貸) 普通預金 50,000
- (借) 買掛金 50,000 / (貸) 普通預金 50,000
- (借) 前払金 50,000 / (貸) 普通預金 50,000
答えを見る
【A2】3. (借) 前払金 50,000 / (貸) 普通預金 50,000
解説:商品はまだ受け取っていません。手付金(内金)は「前払金」(資産)として処理します。この時点では「仕入」(費用)は発生しません。
【Q3】上記Q2の商品300,000円が納品され、手付金50,000円を差し引いた残額250,000円を現金で支払った。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 仕入 250,000 / (貸) 現金 250,000
- (借) 仕入 300,000 / (貸) 現金 300,000
- (借) 仕入 300,000 / (貸) 前払金 50,000 / (貸) 現金 250,000
答えを見る
【A3】3. (借) 仕入 300,000 / (貸) 前払金 50,000 / (貸) 現金 250,000
解説:商品を受け取ったので、まず「仕入」(費用)が全額の300,000円発生します(借方)。
貸方は、使われた「前払金」(資産の減少)50,000円と、新たに支払った「現金」(資産の減少)250,000円です。
今回は「お金や権利が一時的に動く」取引を学びました。これらはすべて「資産」のグループでしたね。
次回は、これらと対になるような取引、つまり「お金を一時的に預かる」または「商品以外で未回収のお金がある」場合の処理を見ていきます。「未収入金」「前受金」「預り金」といった、似ているけれど重要な勘定科目を整理します!お楽しみに!