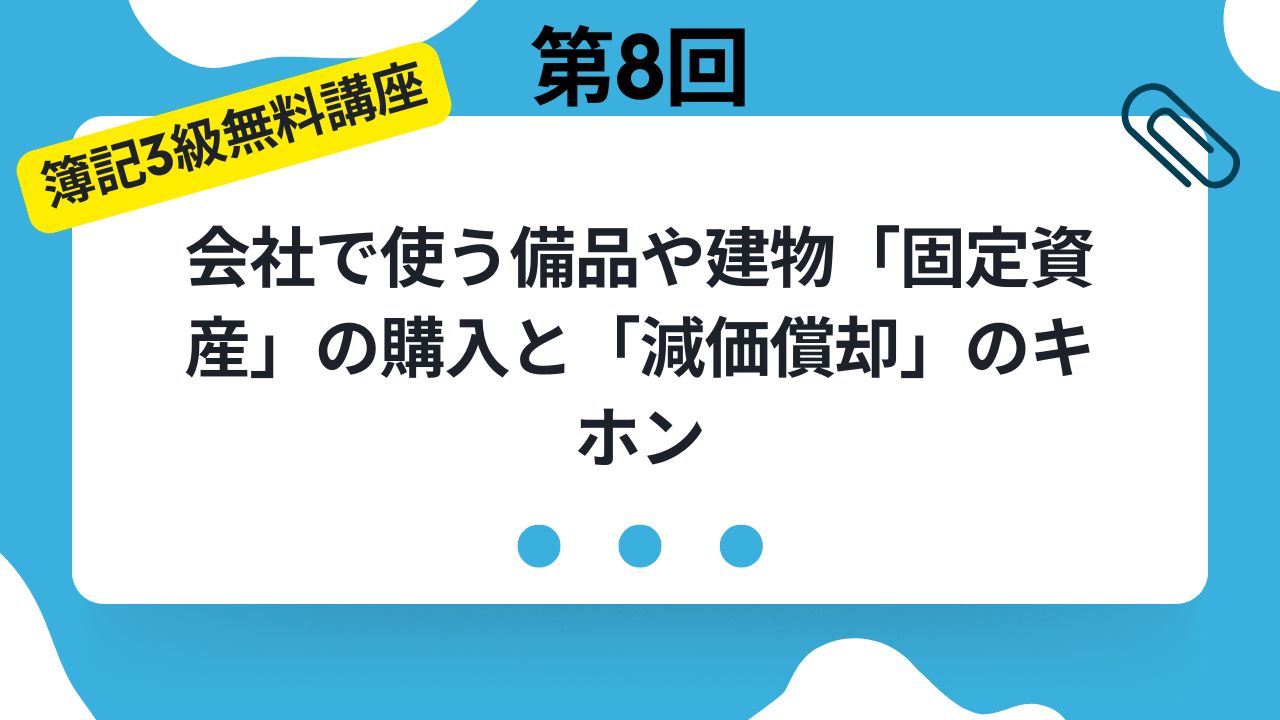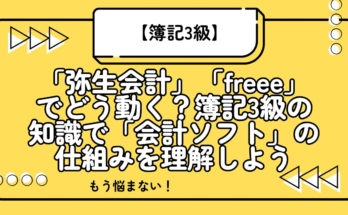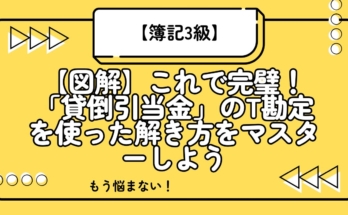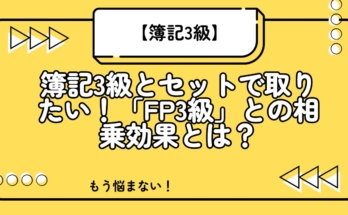こんにちは!「簿記3級合格へ導く!無料Web講座」へようこそ。
第7回までで、会社の日々の中心的な活動である「商品売買」に関する一連の仕訳(現金、掛け、手形)を学びました。仕入、売上、売掛金、買掛金、受取手形、支払手形は、もうバッチリですね!
さて、会社が活動するためには、商品以外にも色々なモノが必要です。例えば、パソコン、机、車、オフィスとなる建物など…。これらは売るためではなく、会社が長期間(通常1年以上)にわたって事業で使うために保有するものです。
今回は、こうした「長期間使うモノ」である「固定資産」の会計処理について学びます。購入時のルールと、簿記3級の最重要論点の一つである「減価償却」の基本をしっかり押さえましょう!
今日のゴール
- 「固定資産」とは何か、具体例がわかる
- 固定資産を購入したときの仕訳ができる(特に「未払金」の使い方をマスターする)
- 購入時にかかった手数料などの「付随費用」の処理がわかる
- なぜ「減価償却」という考え方が必要なのか理解する
- 「減価償却」の基本的な計算(定額法)と仕訳ができる
「固定資産」とは?
固定資産とは、会社が販売目的ではなく、長期間(1年以上)にわたって事業のために使用する財産のことです。簿記3級では、特に形のある「有形固定資産」が中心となります。
これらはすべて「資産」のグループです。
<簿記3級でよく出る有形固定資産>
- 建物:社屋、店舗、倉庫など
- 備品:パソコン、机、椅子、コピー機、応接セットなど
- 車両運搬具:営業用の自動車、トラック、バイクなど
- 土地:社屋や店舗の敷地、駐車場など
固定資産の「購入」時の仕訳
固定資産(資産)を購入したので、資産が増加します。仕訳は簡単ですね。
- 固定資産(資産)が増えたら → 借方(左側)に「建物」「備品」など
【重要】商品以外の「掛け」は「未払金」!
ここで非常に重要なルールがあります。
第6回で、商品を掛けで「仕入れた」とき、「買掛金」(負債)を使うと学びました。
しかし、固定資産(備品や建物など)を「掛け」で買った(後払い)場合、「買掛金」は使いません。
この場合は「未払金(みばらいきん)」という勘定科目(負債)を使います。
<使い分けのルール>
- 商品を掛けで買った → 買掛金(負債)
- 商品以外(固定資産など)を掛けで買った → 未払金(負債)
これは試験で頻繁に問われるひっかけポイントです。必ず区別してください!
設例①:備品を現金で購入した
【設例1】営業用のパソコン50,000円を購入し、代金は現金で支払った。
【考え方】
- 「備品」(資産)が50,000円増えた → 借方(左)に「備品 50,000」
- 「現金」(資産)が50,000円減った → 貸方(右)に「現金 50,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 備品 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
設例②:備品を「掛け」で購入した(最重要!)
【設例2】応接セット100,000円を購入し、代金は来月末に支払うことにした(掛け)。
【考え方】
- 「備品」(資産)が100,000円増えた → 借方(左)に「備品 100,000」
- 商品以外の掛けなので、「未払金」(負債)が100,000円増えた → 貸方(右)に「未払金 100,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 備品 | 100,000 | 未払金 | 100,000 |
※貸方を「買掛金」にしないよう、絶対に注意してください!
【重要】購入時の手数料(付随費用)の処理
第5回で、商品を仕入れたときの送料(仕入諸掛)は「仕入」勘定に含めると学びました。
固定資産もルールは同じです。
固定資産を購入するためにかかった手数料や送料(付随費用)も、その固定資産の金額(取得原価)に含めます。
設例③:付随費用を含めて購入した
【設例3】営業用の自動車1,000,000円を購入し、代金は小切手を振り出して支払った。また、登録手数料50,000円は現金で支払った。
【考え方】
- 車の本体価格1,000,000円+登録手数料50,000円=1,050,000円が、今回の「車両運搬具」の取得原価です。
- 「車両運搬具」(資産)が1,050,000円増えた → 借方(左)に「車両運搬具 1,050,000」
- 「当座預金」(資産)が1,000,000円減った → 貸方(右)に「当座預金 1,000,000」
- 「現金」(資産)が50,000円減った → 貸方(右)に「現金 50,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 1,050,000 | 当座預金 | 1,000,000 |
| 現金 | 50,000 |
※このように、借方が1行、貸方が2行になる仕訳も普通にあります(逆も然りです)。借方合計と貸方合計が一致していればOKです。
「減価償却」とは?(決算時の処理)
さて、固定資産の処理で最も大事なのが「減価償却」です。これは購入時ではなく、年に一度の「決算」のときに行う処理です。
なぜ減価償却が必要なの?
例えば、100万円の車(固定資産)を買ったとします。この100万円は、買ったその日だけに使われるのではなく、例えば5年、10年と長期間にわたって会社の売上を稼ぐために活躍しますよね。
もし、買った年に100万円すべてを「費用」として計上してしまうとどうでしょう?
- 買った年:費用が100万円も発生し、利益が不当に少なくなる。
- 2年目以降:車を使っているのに費用はゼロ。利益が不当に多くなる。
これでは、会社の正しい成績(利益)が計算できません。
そこで、「固定資産の購入代金を、それが活躍する期間(耐用年数)にわたって、少しずつ費用として配分しよう」という考え方が生まれました。この手続きを「減価償却」、このとき計上する費用を「減価償却費」といいます。
減価償却の対象にならないもの
注意点として、使っても価値が減らない(と考えられている)資産は減価償却を行いません。
代表例は「土地」です。土地は時間が経っても老朽化しないため、減価償却の対象外です。
減価償却の計算方法:「定額法」
費用の配分方法にはいくつかありますが、簿記3級で学ぶのは最も簡単な「定額法」です。これは、毎年「一定額」ずつ費用を計上していく方法です。
計算式は以下の通りです。
- 取得原価:その資産の購入代金(付随費用も含む)
- 残存価額:耐用年数が終わったときに、どれくらいの価値が残っているかという見積額。(簿記3級では「取得原価の10%」または「ゼロ」が主流です)
- 耐用年数:その資産が事業で使えると見積もられる年数
減価償却の仕訳:「間接法」
計算した「減価償却費」を仕訳します。簿記3級では通常「間接法」という方法を使います。
これは、固定資産の価値(備品や建物)を直接減らすのではなく、「減価償却累計額」という勘定科目(資産のマイナスを意味する)を使って、間接的に価値の減少を記録する方法です。
仕訳の形は毎年同じです。この形を丸ごと覚えてしまいましょう!
【仕訳の型】(決算整理仕訳)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | (計算額) | 減価償却累計額 | (計算額) |
- 減価償却費(費用):費用の発生 → 借方(左)
- 減価償却累計額(資産のマイナス):資産のマイナスが増加 → 貸方(右)
設例④:減価償却の計算と仕訳
【設例4】決算日(3月31日)になった。期首(4月1日)に購入した備品(取得原価100,000円、耐用年数5年、残存価額は取得原価の10%)について、定額法により減価償却を行う。
【考え方】
1. 減価償却費の計算
- 取得原価:100,000円
- 残存価額:100,000円 × 10% = 10,000円
- 耐用年数:5年
(100,000円 - 10,000円) ÷ 5年 = 18,000円
2. 仕訳
- 「減価償却費」(費用)が18,000円発生した → 借方(左)に「減価償却費 18,000」
- 「減価償却累計額」(資産のマイナス)が18,000円増えた → 貸方(右)に「減価償却累計額 18,000」
【仕訳】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 18,000 | 減価償却累計額 | 18,000 |
※来年も、再来年も、耐用年数が終わるまで毎年この仕訳を繰り返します。(これが「定額法」です)
POINTまとめ
- 1年以上使うモノ(備品、建物、車両、土地など)は「固定資産」(資産)として処理する。
- 固定資産の購入費用(付随費用)は、取得原価(その資産の金額)に含める。
- 商品を仕入れた時の掛けは「買掛金」(負債)。
- 固定資産を買った時の掛けは「未払金」(負債)。この区別は超重要!
- 「減価償却」とは、固定資産の価値の減少を、耐用年数にわたって費用配分する手続き。
- 「土地」は価値が減らないので減価償却はしない。
- 減価償却費の仕訳は、(借)減価償却費 / (貸)減価償却累計額 の形を覚える。
ミニクイズ
お疲れ様でした!「固定資産」と「減価償却」は、簿記3級の後半(決算)で非常に重要になる論点です。基本をしっかり固めましょう。
【Q1】営業用のパソコン120,000円を購入し、代金は来月支払うことにした(掛け)。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 仕入 120,000 / (貸) 買掛金 120,000
- (借) 備品 120,000 / (貸) 買掛金 120,000
- (借) 備品 120,000 / (貸) 未払金 120,000
答えを見る
【A1】3. (借) 備品 120,000 / (貸) 未払金 120,000
解説:パソコンは「備品」(固定資産)です。固定資産を掛けで買った場合は「未払金」(負債)を使います。「買掛金」は商品を仕入れたときだけです!
【Q2】店舗用の建物5,000,000円を購入し、仲介手数料200,000円とともに小切手を振り出して支払った。このときの借方(左側)の勘定科目と金額として正しいものはどれ?
- (借) 建物 5,000,000 と (借) 支払手数料 200,000
- (借) 建物 5,200,000
- (借) 土地 5,200,000
答えを見る
【A2】2. (借) 建物 5,200,000
解説:固定資産を購入するための付随費用(仲介手数料)は、取得原価に含めます。したがって、5,000,000円+200,000円=5,200,000円が「建物」(資産)の金額となります。(貸方は「当座預金 5,200,000」です)
【Q3】決算にあたり、車両(取得原価1,000,000円、耐用年数5年、残存価額ゼロ、定額法)の減価償却を行う。このときの仕訳として正しいものはどれ?
- (借) 減価償却費 200,000 / (貸) 減価償却累計額 200,000
- (借) 減価償却費 200,000 / (貸) 車両運搬具 200,000
- (借) 車両運搬具 200,000 / (貸) 減価償却累計額 200,000
答えを見る
【A1】1. (借) 減価償却費 200,000 / (貸) 減価償却累計額 200,000
解説:まず計算します。(1,000,000円 – 0円)÷ 5年 = 200,000円。
仕訳の形は(借)減価償却費 / (貸)減価償却累計額 です。これが間接法による記帳です。
今回は「固定資産」と「減価償却」という、決算にも関わる大きな論点を学びました。「減価償却」は今後、決算整理編(第4部)でさらに詳しく(期中に購入した場合の月割計算など)学びますが、まずは今日の基本をしっかり押さえてください。
次回からは、日々発生する様々な「費用」や「収益」の仕訳を見ていきます。お楽しみに!