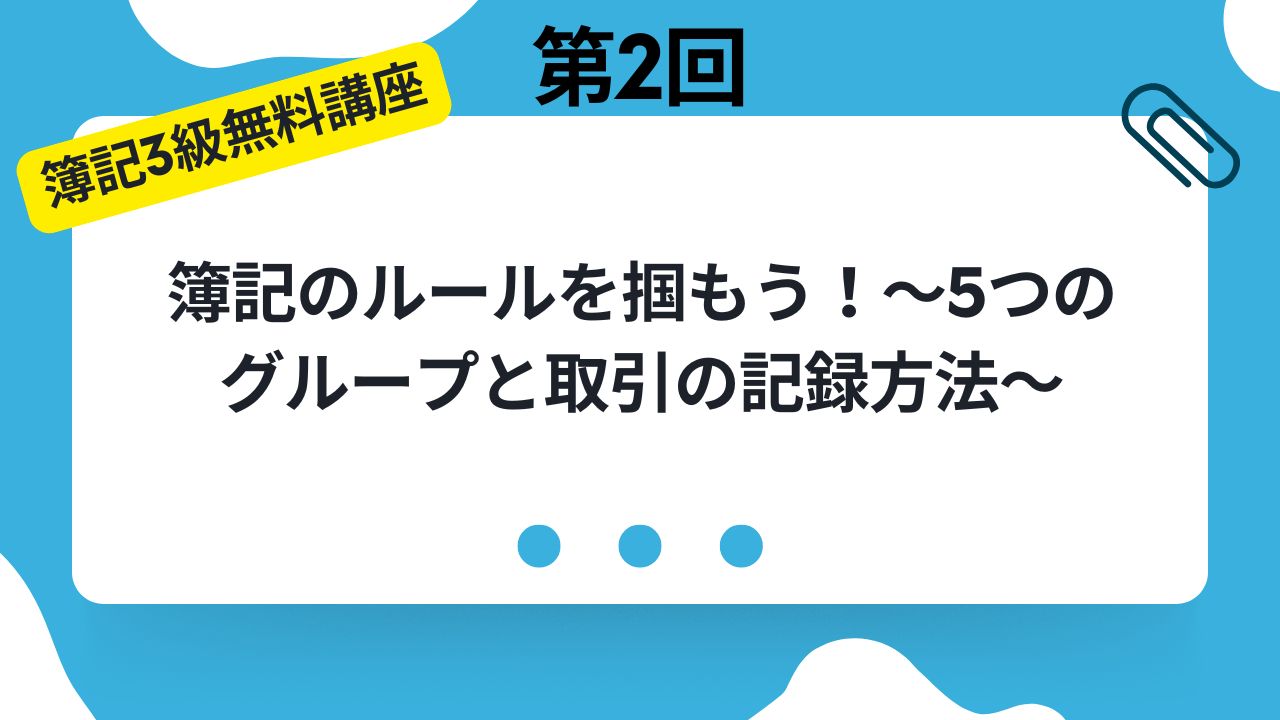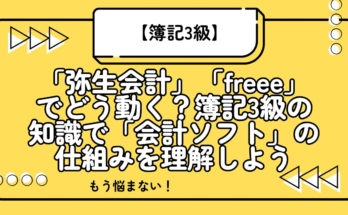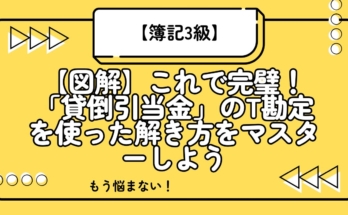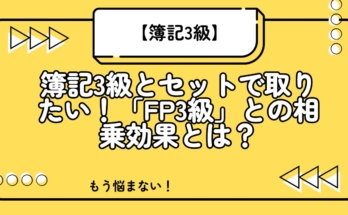簿記3級合格へ導く!無料Web講座、第2回へようこそ!
前回(第1回)は、「簿記とは何か?」そして最終ゴールである「貸借対照表(B/S)」と「損益計算書(P/L)」について学びましたね。
今回は、いよいよ簿記の具体的な記録ルールを学びます。 なぜ簿記が「難しい」と感じるかというと、この最初のルールでつまずいてしまうからです。
でも安心してください! このルールさえ掴んでしまえば、簿記の8割は理解したと言っても過言ではありません。 自転車の乗り方と同じで、一度覚えれば一生モノのスキルになります。 ゆっくり、確実にマスターしていきましょう!
今日のゴール 🏁
- 簿記の世界で使われる5つのグループ(登場人物)を覚える。
- 5つのグループがB/SとP/Lのどこに配置されるか(ホームポジション)を理解する。
- 取引があったとき、5つのグループが**「増える」「減る」のルール**を掴む。
簿記の世界の5つの主人公(5つのグループ)
簿記で記録する会社のお金やモノの動き(取引)は、すべて次の5つのグループのどれかに分類されます。
- 資産
- 会社が持っている「プラスの財産」。
- 例:現金、預金、建物、土地、商品、売掛金(後でもらえるお金)など。
- 負債
- 会社が返済・支払う義務がある「マイナスの財産(借金)」。
- 例:借入金、買掛金(後で払うお金)など。
- 純資産
- 会社の「正味(しょうみ)の財産」。元手とも言います。
- 計算式:資産 − 負債 = 純資産
- 例:資本金(株主が出したお金)、利益剰余金(過去の儲けの蓄積)など。
- 収益
- 会社が稼いだ「儲けの原因」。
- 例:売上、受取利息など。
- 費用
- 儲けのために使った「出費の原因」。
- 例:仕入、給料、家賃、広告費、支払利息など。
【コラム:B/SとP/Lの関係】 第1回で学んだ2つの成績表を思い出してください。
- 貸借対照表 (B/S): 財産の状態(資産、負債、純資産)
- 損益計算書 (P/L): 経営成績(収益、費用)
そう、この5つのグループは、B/SとP/Lを作るための部品なんです!
5つのグループの「ホームポジション」を覚えよう!
ここが最重要ポイントです! 5つのグループには、それぞれB/SとP/Lの中に「定位置(ホームポジション)」が決まっています。
「ホームポジション = 増えたときに記録する側」と覚えてください。
まずは、前回見たB/SとP/Lの箱を思い出してください。 必ず「左側」と「右側」に分かれていましたね。
貸借対照表 (B/S)
資産
(ホームポジション:左)
負債
(ホームポジション:右)
純資産
(ホームポジション:右)
損益計算書 (P/L)
費用
(ホームポジション:左)
収益
(ホームポジション:右)
まとめると、ホームポジション(=増えたら書く側)はこうなります。
- 左側グループ: 資産、費用
- 右側グループ: 負債、純資産、収益
まずは「資産は左、負債は右」だけでも覚えてみてください。 自然とB/Sの形が頭に入ってきます。
取引の記録ルール(増減)
ホームポジションを覚えたら、ルールはもう簡単です。
- そのグループが増えたら → ホームポジション側 に書く
- そのグループが減ったら → ホームポジションと反対側 に書く
これだけです!
5つのグループの増減ルール
ホームポジションが「左」のグループ
【資産】
【費用】
ホームポジションが「右」のグループ
【負債】
【純資産】
【収益】
すべての取引は「原因と結果」のセット(取引の二面性)
最後のルールです。 簿記の記録は、必ず「左側」と「右側」の2つをセットで記録します。 これを「取引の二面性(にめんせい)」と呼びます。
なぜなら、どんな取引も「原因」と「結果」が必ずあるからです。
例:「現金が100円増えた」
- なぜ? → 「商品を売ったから」(原因)
- 結果 → 「現金が増えた」(結果)
これを簿記のルールで記録すると…
- 「商品を売った」=収益の発生 → ホームポジション「右」
- 「現金が増えた」=資産の増加 → ホームポジション「左」
となり、必ず「左」と「右」の両方が動きます。 そして、このとき左右の金額(この例では100円)は必ず一致します。 これを「貸借平均の原理」と呼びます。
やってみよう!記録の練習
ルールがわかったところで、簡単な取引を「左」と「右」に分けてみましょう。 (これが次回の「仕訳」の土台になります!)
【例題1】銀行から10万円を借りて、現金で受け取った。
- ステップ①(原因): 銀行からお金を借りた
- →「借入金(負債)」が10万円増えた。
- → 負債のホームポジションは「右」。
- ステップ②(結果): 現金を受け取った
- →「現金(資産)」が10万円増えた。
- → 資産のホームポジションは「左」。
- 記録の結果
- 【左】現金 10万円
- 【右】借入金 10万円
- (左右の金額が一致しましたね!)
【例題2】文房具(消耗品)を5千円分、現金で買った。
- ステップ①(原因): 文房具を買った
- →「消耗品費(費用)」が5千円発生した。(費用が増えた)
- → 費用のホームポジションは「左」。
- ステップ②(結果): 現金で支払った
- →「現金(資産)」が5千円減った。
- → 資産のホームポジションは「左」。減った場合はその反対側なので「右」。
- 記録の結果
- 【左】消耗品費 5千円
- 【右】現金 5千円
- (今回も左右の金額が一致しました!)
POINTまとめ 💡
- 簿記のグループは「資産・負債・純資産・収益・費用」の5つ。
- ホームポジション(増えたら書く側)を覚える!
- 左側:資産、費用
- 右側:負債、純資産、収益
- ルールは「増えたらホームポジション側、減ったら反対側」。
- 取引は必ず「左」と「右」のセットで記録し、左右の金額は必ず一致する(貸借平均の原理)。
ミニクイズ ✏️
今日のルール、覚えられましたか?
Q1. 会社のプラスの財産である「資産」グループ。ホームポジション(増えたときに記録する側)はどちらでしょう?
- 左
- 右
Q2. 会社の儲けの原因である「収益」グループ。ホームポジション(発生したときに記録する側)はどちらでしょう?
- 左
- 右
・・・
【解答】 Q1 → 1. 左 Q2 → 2. 右
お疲れ様でした! この「5つのグループ」と「左右の増減ルール」は、簿記を学習する上で心臓部となる、最も大切なルールです。
今日の内容が完璧に理解できなくても大丈夫です。 次回から学ぶ「仕訳(しわけ)」の練習を繰り返すうちに、自然と身についていきます。
次回は、いよいよ簿記の基本作業「仕訳」と、グループの具体的な名前「勘定科目」について徹底解説します!